足の骨格が崩れることで起こる代表的な不具合の一つは何といっても外反母趾でしょう。
酷くなると痛みが出て病院で治療を受ける方も多いですが、病院へ行くほどではない軽度の外反母趾の方はとても多いと思います。
外反母趾の原因として真っ先に挙げられるのが、つま先が細くなった靴を履くこと。特にヒールの高い靴は母趾に強い力がかかるため更に変形を助長すると言われています。
そのため、先端が太めの形状のヒールがない靴を履けば外反母趾にならないと誤解している方は少なくありません。確かに、手術が必要になるような外反母趾はつま先が細くヒールが高い靴を履いていたことが原因の一つになるでしょう。しかし、先端が太めの形状でヒールが低い靴しか履かない方でも軽度の外反母趾になる場合はあります。
では、外反母趾の根本的な原因は何でしょうか?
それは、アーチが崩れた状態で歩くことです。
では、崩れた足と整った足の地面の蹴り方の違いを実際に見てみましょう。
崩れた足の場合、地面を蹴る支点は母趾球のみのため、この1点に体重の全てをかけることになります。その後、母趾の先端まで地面に押し付けながら地面を蹴る動作が続くので、ヒールが低い靴しか履いていなくても外反母趾になるというわけです。このように足の骨格が崩れた状態で歩くと、必然的に母趾球から先端にかけて大変な負担をかけてしまうのです。
このときに使う筋も確認しておきましょう。
踵を上げた瞬間から、母趾球の側面だけを支点に足を上げる状態で、踵を上げるときに使う筋は主にアキレス腱につながるふくらはぎの筋(下腿三頭筋)のみです。足裏にある母趾球の底面で地面を押さえるための筋やその他の指を曲げるための筋はほとんど使いません。つまり、歩行中に趾は全く使えていません。特に問題なのは、母趾をほとんど使えていないことです。
一般的に、「歩くときは趾(あしゆび)を使って地面を蹴るのが良い」と聞きますが、多くの方が、「(崩れた足の場合のように、)母趾球の側面だけを支点にして踵を下腿三頭筋だけで上げて地面を蹴るのが良い」というように誤解しています。
では、趾を使って地面を蹴るとはどういう足の使い方なのでしょうか?
それが、アーチが整った足で地面を蹴るときの足の使い方なのです。
その動画を見てみましょう。
アーチが整っているので、進行方向に対して趾は真っ直ぐ前を向き、母趾球と小趾球が同時にそれぞれの底面で地面をぐっと押さえた状態で踵を上げていきます。このとき、足の甲や底面に複数ある各趾を動かす筋が使われます。特に母趾球の底面で地面をぐっと押さえるための筋(短母趾屈筋、長母趾屈筋)が強く働き、足全体が動かないようにしっかり支えてくれます。そのため、崩れた足の時とは全く異なり、趾を動かす筋を複数しっかりと使って地面を蹴ることになります。
また、動画からも分かるように、足全体が地面に対して前に押し出されるだけで、先ほどの崩れた足のように外側に向けて斜めに動くことはありません。
靴を履いていると小指、薬指、中指の上部が痛くなる(靴と足と脚(1)参照)もこの動画と同じ状況です。全て、根っこは同じ原因です。
今回は、外反母趾の根本的な原因について、足のアーチとの関係を説明しました。
くれぐれも、「趾(あしゆび)を使って歩く」ということを、「母趾球の側面だけを地面に押し付けて踵を上げる」歩き方と誤解しないでください。この誤解をしたまま、間違った足の使い方で歩いていると、外反母趾は酷くなっていってしまいますので、ご注意ください。
大切なのは、「母趾と小趾の両方を地面に接地させながら踵を上げる」=「アーチが整った状態で踵を上げる」という歩き方です。
ちなみに、このような歩き方(アーチが整った状態で踵を上げる)ができていない場合の足のサインは、母趾球と母趾側面(外側)付近のタコです。この場所にタコができている方は要注意です。
このような足の使い方は、なるべく若いうちに見直すことをお勧めします。
足の使い方に問題があるまま高齢になると、歩行しにくくなってとても苦労します。(「高齢者への靴の適用事例/母趾が痛くて歩きたくない!が見事に解決」参照)
それでは、また。



2_アートボード-1-scaled-e1750677192887-800x480.jpg)

3_アートボード-1-scaled-e1750677330148-200x200.jpg)
8-e1766480826390-500x333.jpg)
5_アートボード-1-scaled-e1750677666162-500x333.jpg)
1_アートボード-1-scaled-e1750677002999-500x333.jpg)
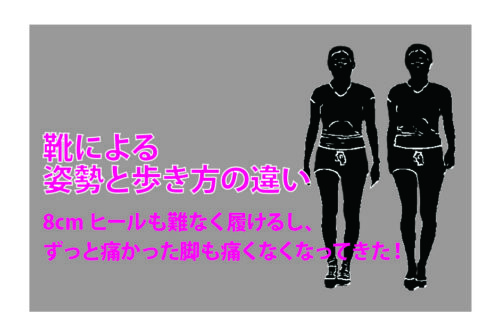
7-e1766141143390-500x333.jpg)


この記事へのコメントはありません。